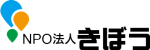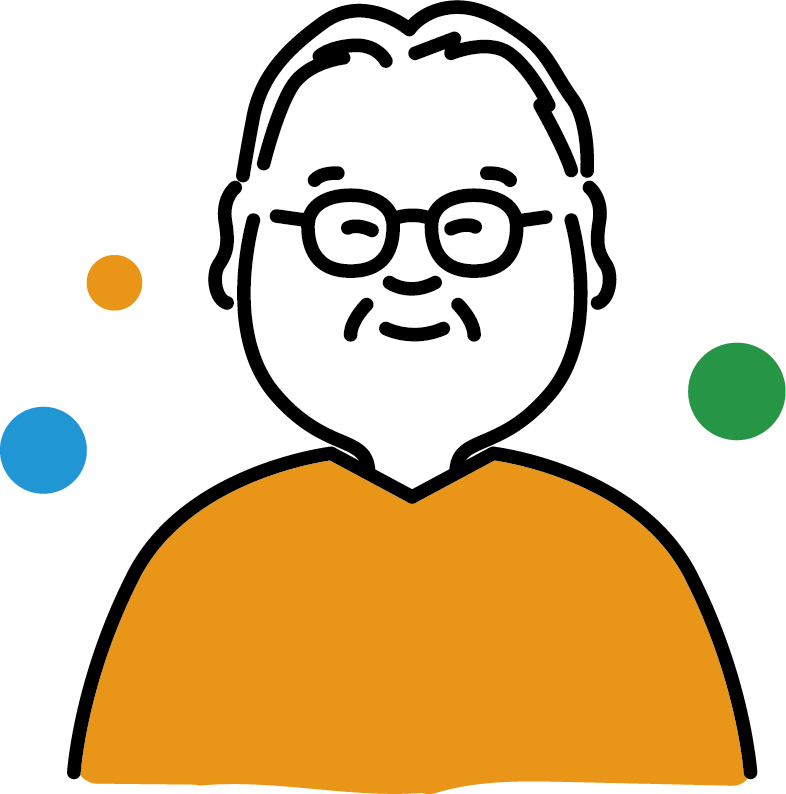暑い暑い夏休みが終わり、子どもたちは、それぞれの学校に登下校する日々にもどりました。
いまは、教育の在りかたについてさまざまな考えがあり、当たり前のこととされてきた「学校へ行くこと」でさえ、その是非を問う意見があります。
特に、不登校の児童生徒については、「無理に行かなくていい」という対応が良いとされています。
学校生活に何らかの理由でしんどさを感じていながらも、頑張って学校通っていたけれど、ついに耐えられなくなって「学校に行きたくない」と訴える子が多いと言われています。そのため、「つらいことから一時的に避難する」「安心できる居場所で過ごす」「心の充電をする」時間が必要な
なのです。
もとより、これが唯一無二、最上最善の対応だとは思いませんが、子ども側の視点に立ったかかわりは大切だと思います。
ジャンプ教室にも不登校だった子がいました。その子は、ある年の4月から週に複数回の学習支援に来ました。不登校といっても全く学校に行かないことはなく、週に1回、自分が決めた日の1時限のみ登校していました。ジャンプ教室は、夏休みにはいると、利用時間が午前から夕方になります。彼は、前半こそ「しんどい」「疲れた」と言っていたのですが、利用を予定していた日は、1度も休むことなく来所しました。
そして、彼は、夏休みの最終日にこう言いました。
「9月から毎日4時限目まで学校へ行く」
ビックリして、「大丈夫なの」と聞くと「ジャンプ教室で慣れた」と返事をしたのです。私は「こんなこともあるんだ」と驚きました。
ジャンプ教室が、彼にとって「心地良い居場所」「心の充電場所」なったのであれば、このうえない喜びです。また、指導員の皆さんの声掛けが、一歩踏み出すための追い風になったのかもしれません。
彼の変化は、私にとって、放課後デイサービスのあるべき姿のヒントをくれたように思います。
この出来事のあと、ある一文を知ることになりました。タイトルは「なぜ子供は学校に行かねばならないのか」。ノーベル賞作家大江健三郎さんの著書『「自分の木」の下で』(朝日新聞社 2001年7月1日第1刷発行)に収められています
「私はこれまでの人生で二度、そのことについて考えました。」という書き出しではじまり、著者が10歳の時と著者の長男が高校を卒業した時の2つのエピソードをつづりながら、それぞれの時に考えたことを紹介しています。私が印象に残っているのは、著者が10歳の時の話で、病気から回復して学校にもどったときに、看病をしてくれた母との会話を思いながら次のように考えます。
”この教室や運動場にいる子どもたちは、みんな、大人になることができな
いで死んだ子供たちの、見たり聞いたりしたこと、読んだこと、自分でし
たこと、それを全部話してもらって、その子供たちの代わりに生きている
のじゃないだろうか。(略)
そして僕らはみんな、その言葉をしっかり自分のものにするために、学校
へ来ているのじゃないか? 国語だけじゃなく、理科も算数の、体操です
らも、死んだ子供ら言葉を受けつぐために必要なのだと思う!(略)だか
ら、僕らは、このように学校に来て、みんなで一緒に勉強したり遊んだり
しているのだ……”(14ページ 5行目から14行目 抜粋)
こんなことを10歳の少年が考えるのか、という驚きとともに、妙に納得しました。この年は終戦の年で、今とは時代が全く異なりますが、私は、大江少年の考えにリアリティーを感じます。
毎日学校に行くことが奇跡のように思える昨今、子どもたちにとって、楽しいはずの学校が、戦いの場にならないことを切に願います。
2024.9.24